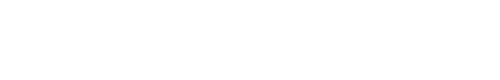2025/10/17
「就労移行支援」ってなに?サービスの内容や使い方をやさしく解説!

スタッフ
こんにちは!障がい者のための在宅就労求人.comです。
今日は就労移行支援についてお話していきます。
目次
- 就労移行支援ってどんなサービス?わかりやすく紹介!
- 就労移行支援を利用するメリットとは?
- 就労移行支援を利用できる条件とは?
- 就労移行支援を利用するまでの5つのステップ
- 就労移行支援のスケジュールと利用期間〜どんなふうに進むの?〜
- 就労移行支援を利用する費用について──安心して利用できる料金制度
- 自分らしい「働く」を見つけるために──就労移行支援という選択肢
就労移行支援ってどんなサービス?わかりやすく紹介!
「就労移行支援って聞いたことはあるけど、実際にどんなことをするの?」
そんな疑問を持っている方のために、この章では就労移行支援で受けられる主なサポート内容をわかりやすく紹介します。
1. 職業訓練でスキルアップ!
まずは、働くためのスキルを身につける「職業訓練」です。
たとえば、パソコンの基本操作や書類作成、データ入力といった事務作業の練習、接客対応のロールプレイなど、自分の目指す仕事に合わせた実践的な訓練を受けることができます。
「働くのが初めて」「ブランクがあって不安」という方も、基礎から学べる環境が整っています。
2. 就労準備プログラムで職場に慣れる
就労移行支援では、スキルだけでなく「働く習慣」を身につけるための準備プログラムも用意されています。
時間通りに通所する練習や、職場で求められるコミュニケーションの取り方、ビジネスマナーなど、仕事をするうえで欠かせない基本をじっくり学ぶことができます。
「生活リズムを整えるところから始めたい」という人にも安心の内容です。
3. 職場実習でリアルな体験
支援事業所を通じて、実際の職場での実習に参加することもできます。
これは、「本当にこの仕事が自分に合っているのか?」を実際に体験しながら確認できる大切なステップです。
職場の雰囲気や仕事の流れを肌で感じることで、就職後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
4. 就職活動のサポートもバッチリ
就労移行支援では、就職活動そのものを手厚くサポートしてくれます。
履歴書や職務経歴書の作成方法を教えてくれるだけでなく、面接の練習や求人の紹介、応募書類の添削などもしてくれます。
「どうやって就職活動を進めたらいいかわからない」という方でも、プロの支援員と一緒に計画を立てながら安心して進めていけます。
5. 働き始めた後も安心の定着支援
就職はゴールではなくスタート。
就職後も、職場にしっかりと定着できるように、定期的に相談に乗ってくれたり、職場との連携をとってくれたりする「定着支援」もあります。
たとえば、「職場で困っているけどどう伝えたらいいかわからない」といったときにも、支援スタッフが間に入ってくれることもあります。
就労移行支援を利用するメリットとは?
就労移行支援は、ただ「仕事を探す」だけの場所ではありません。
実は、働きたいと考えている障がいのある方にとって、とても心強いサポートがたくさん詰まっているサービスなんです。
そんな就労移行支援を利用することで得られる主なメリットを、わかりやすく紹介していきます。
自分を知ることが、働く一歩目に
まず大きなメリットとして挙げられるのが、「自己理解」が深まることです。
就労移行支援では、自分の障がい特性を整理したり、自分にとって得意なこと・苦手なことを把握したりする時間がしっかり取られます。
「自分はどんな働き方が向いているのか」「どんなサポートがあれば力を発揮できるのか」を知ることで、自信を持って就職活動に臨むことができるようになるんです。
また、職場で自分の特性を上手に伝えるためのコミュニケーションスキルも学べます。
これは実際に働き始めたとき、周囲との良い関係を築くうえでとても大切。自分のことをうまく伝える練習を通じて、「理解してもらえる安心感」も得られるようになります。
就職活動の不安も一緒に乗り越えられる
就職活動って、何から始めたらいいのか分からなくなること、ありますよね。
履歴書や職務経歴書の書き方、面接の受け方、求人の探し方……。そんな不安も、就労移行支援ではスタッフが一つひとつ丁寧にサポートしてくれます。
書類作成のコツや、自分のアピールポイントの見つけ方など、実践的なアドバイスが受けられるのも魅力のひとつ。面接対策では、実際にロールプレイをしながら、緊張をやわらげる練習ができるところもあります。
働くためのスキルも習得できる
パソコンの基本操作やビジネスマナー、電話対応、報連相(報告・連絡・相談)といった職場で必要な基礎スキルも、就労移行支援では段階的に学べます。
最近では、ITスキルに特化した支援事業所もあり、プログラミングやWebデザイン、データ入力など、テレワークでも活かせるスキルを学べる場所も増えています。
「自分には特別なスキルなんてない」と思っている方も、一歩一歩ステップを踏んで、自信をつけていくことができます。
就職後も「一人じゃない」安心感
就労移行支援のもうひとつの大きな特徴が、就職したあともサポートが続くということ。
これは「定着支援」と呼ばれるもので、職場で困ったことがあったり、環境に慣れないときに、相談に乗ってくれたり必要に応じて職場と連携をとってくれたりします。
「せっかく就職しても長く続けられるか不安…」という方にとっては、大きな安心材料になります。
就労移行支援には、働くためのスキルや知識だけでなく、心の準備や自己理解といった内面的なサポートも含まれています。自分らしく働くための準備を、誰かと一緒に進められる──これこそが、就労移行支援の最大のメリットなのかもしれません。
就労移行支援を利用できる条件とは?
「就労移行支援を利用したいけれど、自分が対象になるのかよくわからない…」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。実際、就労移行支援は誰でも自由に利用できるサービスではなく、いくつかの利用条件が定められています。
ここでは、就労移行支援を利用するための主な条件やポイントを、わかりやすく解説していきます。
基本的な利用条件
就労移行支援の利用には、以下のような条件があります。どれも重要なポイントなので、当てはまるかどうかを確認してみましょう。
① 年齢が18歳以上65歳未満であること
まず第一に、就労移行支援は18歳以上65歳未満の方が対象です。これは「一般企業などで働くことを目指す」という就労移行支援の目的に基づいたものです。
現在、高校卒業後にすぐ利用する方や、長年のブランクを経て再び就職を目指す50代の方など、年齢層は幅広くなっています。65歳になると原則利用できなくなるため、支援を希望している方は早めの検討がおすすめです。
② 障害者手帳の所持、または医師の診断書があること
次に必要なのが、「障害のあることを証明する書類」です。
多くの場合、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っている方が対象になりますが、手帳を持っていなくても医師の診断書や意見書があれば、利用が認められる場合があります。
特に、発達障害や精神障害をお持ちの方の中には、診断を受けていても手帳を申請していないケースも多いですが、就労移行支援の利用にあたっては、医師の意見書で対応できることもあります。
「手帳がないから無理かも…」とあきらめる前に、まずは自治体や支援事業所に相談してみるのがおすすめです。
③ 一般就労を希望していること(就労意欲があること)
就労移行支援は、一般企業などへの就職を目指す方が対象です。つまり、障がいがあっても「働きたい」という意欲があることが大切です。
「体調が整ってきたから、そろそろ働きたい」「自分らしく働ける職場を探したい」という前向きな気持ちがある方であれば、まずは利用対象と考えられます。
「どんな仕事が向いているかわからない」「働く自信がない」と感じていても大丈夫。支援の中で自己理解を深め、少しずつ準備を整えていくことができます。
④ 現在、失業中であること(在職中は原則対象外)
意外と見落とされがちなのが、「現在失業中であること」です。
就労移行支援は「これから働くことを目指す方」を対象にしているため、基本的には今働いていない人(無職の人)が対象です。
現在アルバイトやパートをしている場合は、利用できない可能性があります。ただし、条件や事業所によっては柔軟に対応されるケースもあるので、まずは相談してみましょう。
障がいの種類は問わないが、個別の配慮が必要
就労移行支援では、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がいなど、幅広い障がいのある方が対象となります。さらに、一定の難病も対象となる場合があります。
それぞれの障がいに応じたサポートが用意されており、最近では発達障がい専門、ITスキル特化型、メンタルサポートに力を入れた事業所など、特色のある施設も増えています。
支援の質や内容は事業所ごとに異なるため、自分の希望や課題に合った施設を選ぶことが、満足のいく支援を受けるカギになります。
条件に当てはまるか不安な場合は、まず相談を
条件を見ると「ちょっとハードルが高いかも…」と思う方もいるかもしれませんが、就労移行支援はひとりひとりの状況に合わせて柔軟に対応してくれる場合が多いです。
手帳を持っていないけれど診断はある
年齢や就労意欲に自信が持てない
働いた経験がほとんどない
こうしたケースでも、利用できた方はたくさんいます。
最初の一歩として、まずは市区町村の障がい福祉窓口や、近くの就労移行支援事業所に気軽に相談してみてください。事前見学や体験プログラムを実施している事業所も多く、自分に合うかどうかを確認してから決められます。
就労移行支援を利用するまでの5つのステップ
「就労移行支援を利用してみたいけど、どうやって始めればいいの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、ここでは利用開始までの流れを5つのステップに分けて、やさしく説明していきます。初めての方でも安心して一歩踏み出せるように、丁寧にご紹介します。
ステップ1:情報を集める・気になる事業所を探す
まずは、自分の住んでいる地域にどんな就労移行支援事業所があるのかを調べましょう。
地域の福祉課やハローワーク、またはインターネットで「地域名+就労移行支援」と検索すると、近くの事業所が見つかります。
最近では、ITスキルに特化したところや、発達障害に強いところなど、事業所ごとに特徴があるので、自分の関心や目指したい仕事に合った場所を探すのがおすすめです。
事業所のホームページには、プログラム内容やスタッフの紹介、実際の利用者の声が載っていることも多く、イメージをつかむのに役立ちます。
ステップ2:見学・体験をしてみる
気になる事業所を見つけたら、見学や体験利用を申し込んでみましょう。
見学では、施設の雰囲気やスタッフの対応、プログラム内容などを直接確認することができます。体験利用では、実際のプログラムに数日参加し、どんなサポートが受けられるか、自分に合っているかを試すことができます。
このステップはとても大事です。自分に合った環境を選ぶことが、長く安心して通うためのカギになります。
質問や不安がある場合は、その場でスタッフに相談してみてください。「こんなことを聞いていいのかな?」と思うようなことでも、丁寧に答えてくれるはずです。
ステップ3:市区町村に「利用申請」をする
利用したい事業所が決まったら、次は市区町村に利用の申請をします。
これは「障害福祉サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」という証明書をもらうための手続きで、就労移行支援を正式に利用するためには欠かせません。
申請に必要なものは、以下のようなものが一般的です:
障害者手帳(または医師の診断書など)
印鑑・本人確認書類
申請書類(事業所や市役所で用意してもらえます)
手続きの中では、生活状況や就労の希望についてのヒアリング(聞き取り)があります。
わからないことがあっても、事業所のスタッフが一緒にサポートしてくれる場合が多いので、心配しすぎなくても大丈夫です。
ステップ4:サービス等利用計画の作成
申請が進むと、次は「サービス等利用計画」の作成に進みます。
これは、「どんな支援をどんな目的で受けるのか」をまとめた計画書です。
この計画は、指定相談支援事業所という第三者が一緒に考えてくれることが多く、自分一人で作る必要はありません。
「こんな仕事をしたい」「まだどんな仕事が向いているかわからない」など、自分の思いや悩みを率直に伝えることで、今の状況に合った支援プランが作られていきます。
ステップ5:受給者証が届いたら利用開始!
市区町村の審査が終わり、「障害福祉サービス受給者証」が発行されたら、いよいよ就労移行支援の利用がスタートです!
この受給者証には、どの事業所でどれくらいの期間、何回通えるかといった情報が記載されています。
事業所との契約手続きを行い、いよいよプログラムへの参加が始まります。
通所初日は緊張するかもしれませんが、多くの人が「思っていたより安心できた」と感じています。焦らず、自分のペースで進めていきましょう。
就労移行支援のスケジュールと利用期間〜どんなふうに進むの?〜
「就労移行支援を利用するって、どんな流れで進むの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。就労移行支援では、利用者一人ひとりの希望や特性に合わせて支援計画が立てられます。そのため、スケジュールも個別に調整されるのが特徴です。
ただし、ある程度の「目安」となる一般的なスケジュールもあります。ここでは、就労移行支援の利用開始から就職、そして就職後のフォローまで、全体の流れを段階ごとにわかりやすくご紹介します。
【1】支援スタート期(開始〜3ヶ月)
最初の数ヶ月は、就労に向けた「準備期間」です。
この時期には、利用者のこれまでの経験や得意・不得意なこと、目指す仕事の方向性などをスタッフと一緒に確認していきます。
また、日々のスケジュールの中では、次のような基本的なスキルを学ぶことが多いです。
コミュニケーションのとり方
ビジネスマナー(あいさつ、報連相など)
時間管理やスケジュールの立て方
ここでの目的は、「働くための土台づくり」。無理なく通う習慣を身につけ、自分に合った支援内容を見つけていく大切な時期です。
【2】専門スキルの習得期(3〜6ヶ月)
ある程度慣れてきたら、次は「仕事に必要なスキル」を本格的に学ぶ期間に入ります。
パソコン操作(Excel・Wordなど)
接客のロールプレイ
軽作業や清掃などの実践的な練習
障がい特性に合わせた集中力やストレス対策のトレーニング
加えて、職場実習の機会が設けられることもあります。これは、実際の企業などに行って、短期間お仕事を体験するものです。
「働くイメージを掴む」「自分の適性を確かめる」「企業側に自分を知ってもらう」など、多くのメリットがあります。
実習後にはフィードバックもあり、自分の課題や強みをさらに明確にすることができます。
【3】就職活動期(6〜12ヶ月)
スキルが身についてきたら、いよいよ就職に向けた本格的な準備に入ります。
履歴書や職務経歴書の作成サポート
面接練習(模擬面接)
ハローワークや求人サイトの使い方
企業研究や求人の見極め方
この時期には、事業所から企業への紹介や、障がい者雇用の求人の紹介があることもあります。スタッフが一緒に面接に同行してくれたり、事前に企業と調整してくれるケースも多く、初めての方でも安心して就活に取り組むことができます。
【4】定着支援期(12〜24ヶ月)
無事に就職が決まった後も、支援は終わりません。
就職後も継続してサポートを受けられる「定着支援」が用意されています。
定期的な面談や電話による相談対応
必要に応じた職場訪問や企業側へのフォロー
仕事内容や人間関係の悩みのサポート
新しい環境に慣れるには時間がかかるもの。特に障がいのある方にとっては、業務の進め方や周囲とのコミュニケーションで不安を感じることもあります。
そんなとき、就労移行支援の定着支援は大きな力になります。困ったときに「話せる場所」があること、それが安心につながるのです。
【5】原則2年。状況に応じて延長も可能
就労移行支援の利用期間は、原則として最長2年間とされています。
ただし、就職が間近である場合や、やむを得ない事情がある場合には、市区町村の判断で延長が認められることもあります。
2年間という枠の中で、「自分のペースで無理なく就労を目指せる仕組み」になっているのが特徴です。
就労移行支援を利用する費用について──安心して利用できる料金制度
「就労移行支援を使いたいけれど、費用はどのくらいかかるんだろう?」
このような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
福祉サービスというと、「お金がたくさんかかるのでは?」と心配になることもありますよね。でも実は、就労移行支援の費用は所得に応じて決まるため、多くの人が無料または少額で利用できる仕組みになっています。
ここでは、就労移行支援を利用するうえでの自己負担額や、実際の負担がどのように決まるのかを、わかりやすく解説していきます。
■ 基本的には「原則無料」で利用できる人が多数
まず押さえておきたいポイントは、多くの方が自己負担なし(0円)で就労移行支援を利用できるということです。
これは、就労移行支援が「障がいのある方の就労を支援するための公的サービス」であるため、負担が大きくならないよう国や自治体が支えているからです。
自己負担額は、厚生労働省が定めた基準に基づき、利用者やその家族の収入状況に応じて3つの区分に分かれています。
■ 自己負担額の3つの区分とは?
就労移行支援の費用負担は、下記のような3つの所得区分に応じて決まります。
所得区分 年収の目安 月額の自己負担上限
① 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 ー 0円
② 市町村民税課税世帯(年収約600万円未満) 約600万円未満 月額上限 9,300円
③ 上記以外の世帯(年収約600万円以上) 約600万円以上 月額上限 37,200円
【①】生活保護世帯・非課税世帯の方は「完全無料」
生活保護を受けている方や、世帯全体が住民税非課税(収入が一定以下)の場合は、自己負担は一切ありません。つまり、まったくお金を払わずにサービスを利用することができます。
「働くことに不安があるけれど、お金の心配があって一歩が踏み出せない…」という方にも安心の制度です。
【②】市町村民税課税世帯(約600万円未満)は「月額上限9,300円」
世帯収入がある程度ある場合でも、月額9,300円が上限です。
たとえば、一人暮らしをしているけれど親が課税世帯だったり、扶養の範囲内でパート勤務している場合などでも、利用者本人の収入や世帯状況を加味してこの区分に当てはまることがあります。
「毎月高額な費用がかかるわけではない」という点で、多くの方が利用しやすい制度になっています。
【③】高収入世帯(約600万円以上)は「月額上限37,200円」
世帯の年収が600万円を超える場合でも、月37,200円が上限です。それ以上の費用はかかりません。
もちろん、この場合も就労移行支援で提供されるサービス内容(訓練・実習・就職サポートなど)をフルに活用することができるため、「投資として考えると非常に価値がある」と感じる方も少なくありません。
■ 利用料金が免除される場合もある?
実は、就労移行支援では「自己負担額が0円になるケース」が非常に多いです。
たとえば次のようなケースでは、多くの場合で無料になります。
障がい者本人が単身で生活しており、収入が少ない
年金のみで生活している
家族が非課税世帯(収入が低め)の場合
生活保護を受けている
「費用が気になるけれど、自分がどこに当てはまるかわからない…」というときは、お住まいの自治体(福祉課)や、利用を検討している就労移行支援事業所に相談してみるとよいでしょう。職員が丁寧に説明してくれますし、利用開始前に費用についての説明や相談の時間がしっかり設けられるのが一般的です。
■ その他にかかる可能性のある費用は?
基本的なサービス内容(訓練、面談、サポート)はすべて上記の負担範囲で提供されますが、別途かかることがある費用もあります。
たとえば…
実習先までの交通費(実費)
自分で使うノートや文具
訓練に必要なパソコンやソフト(※支給や貸与がある場合も)
昼食代(事業所によっては提供されるところもあり)
こういった費用も含めて、トータルでの負担を知りたい場合は、利用前に見学や体験をして確認するのがオススメです。
■ 費用が理由で利用をあきらめないで
「障がいがあっても自分らしく働きたい」──その一歩を支えてくれるのが、就労移行支援です。
費用について心配される方も多いですが、実際には多くの方が無料または負担の少ない範囲で利用しています。就職に向けての支援、専門スキルの習得、そして就職後の定着支援まで、たくさんのサポートが受けられるサービスです。
「自分に合う仕事が見つからない」「働くのが怖い」「面接が不安」
そんな悩みがある方こそ、まずは一度、相談してみてください。きっと費用以上の価値を実感できるはずです。
自分らしい「働く」を見つけるために──就労移行支援という選択肢
ここまで、就労移行支援のサービス内容やメリット、利用できる条件、利用の流れ、スケジュール、そして費用について詳しくご紹介してきました。
「働きたいけど不安がある」「自分に合った職場を探したい」「社会に出る準備がしたい」──そんな想いを持つ障がいのある方にとって、就労移行支援はとても心強いパートナーになります。
この章では、全体のポイントを振り返りながら、あなたが「一歩踏み出す」ために必要なヒントをお届けします。
■ 就労移行支援って、どんなサポートをしてくれるの?
就労移行支援は、ただ「働く場所を紹介する」だけではありません。
働くために必要なスキルの習得
職場でうまくやっていくための心構えやマナーの学習
自分の障がい特性を理解し、職場にどう伝えるかといった自己理解と対話の練習
実際の職場での実習体験
履歴書や面接の就職活動サポート
そして、就職後の定着支援まで
このように、就労移行支援は「働く前」「働く時」「働いた後」までを総合的にサポートしてくれる場所です。
■ 「できないこと」ではなく「できること」に目を向けられる場所
就労移行支援の現場では、「あなたがどんな人か」「何が得意で、何が苦手か」を一緒に見つけてくれます。
発達障害や精神障害、身体障害など、障がいの種類や特性は人それぞれ違います。「周囲に理解してもらえなかった」「職場になじめなかった」という過去がある方も、ここでは無理のないペースで、前を向いていく練習ができます。
支援員と一緒に目標を立てて、一歩ずつステップを踏むことで、少しずつ「自分にもできることがある」という自己肯定感を育てていけるのです。
■ 不安があっても大丈夫。「一人じゃない」から前に進める
働くことに不安を感じるのは、あなただけではありません。
就労移行支援を利用している人の多くが、「ブランクが長くて不安」「うまく働けなかった経験がある」「人と関わるのが苦手」など、いろんな悩みや背景を抱えています。
でも、だからこそ、就労移行支援の支援員はその気持ちを理解し、一緒に歩んでくれる存在なのです。
一人で頑張ろうとしなくてもいい。支援員と一緒に考え、悩み、成長していくプロセスの中で、自分らしい「働く形」がきっと見つかります。
■ 無理なく通える時間・期間も、自分に合わせて調整可能
「毎日通えるか心配…」「体力的に不安がある」という声もあります。
就労移行支援では、通所日数や時間も、最初は週2〜3回、午前中だけなど、あなたの体調や生活に合わせて柔軟にスタートすることができます。
また、プログラム全体の期間も原則2年以内とされていますが、必要に応じて延長が認められるケースもあるため、「焦らず、じっくり自分のペースで進めたい」という方も安心して利用できます。
■ 利用までのハードルも、意外と低い
就労移行支援を利用するために必要な条件は主に以下の通りです。
18歳〜65歳未満であること
障害者手帳を持っている(または医師の意見書がある)
働く意欲があること
現在、就業していないこと(失業中)
このように、特別なスキルや経験がなくても利用できるのが大きな特徴です。
「これから就職を目指したい」「一人での就職活動が難しい」そんな方には、まさにぴったりのサポートです。
■ 費用面も心配いらないから、安心して始められる
費用についても多くの方が「無料」または「負担の少ない金額」で利用できます。
たとえば、生活保護や住民税非課税世帯であれば完全無料、年収600万円未満の世帯であっても月9,300円が上限です。
これだけ手厚いサポートが受けられるのに、これだけの負担で済むのは、公的支援だからこそ。
「お金のことが心配で、なかなか動き出せない」という方にも、ぜひ知ってほしい制度です。
■ まずは「見学」や「体験」からでOK!
「いきなり利用するのは不安…」「雰囲気が合うか心配…」という方は、まずは見学や体験からスタートしてみるのがおすすめです。
多くの就労移行支援事業所では、無料で見学や体験ができます。
実際に施設の中を見たり、支援員と話してみたりすることで、「ここなら通えそう」「思っていたより優しい雰囲気だな」と感じることができるかもしれません。
■ 自分らしい「働き方」は、きっと見つかる
障がいがあるからといって、「働けない」「キャリアを諦めるしかない」と決めつける必要はありません。
あなたに合った仕事や職場環境、自分の強みを活かせる働き方は、きっとあります。
その第一歩をサポートしてくれるのが、就労移行支援です。
「自分には何ができるのか、わからない」
「一人じゃ就職活動が不安」
「ゆっくりでもいいから、働く準備を始めたい」
そんな想いを持っているなら、まずは一度、就労移行支援の門をたたいてみてください。
あなたの未来は、まだまだこれからです。
「あなたらしい働き方」を、一緒に探していきましょう。
スタッフコラムのおすすめ記事
-
2025/10/17
「就労移行支援」ってなに?サービスの内容や使い方をやさしく解説!
-
2025/05/20
障がい者雇用の魅力的な職種とは?求人の種類とおすすめのお仕事
-
2025/05/20
障がいがあっても大丈夫。自分らしい働き方を家族と一緒に見つけよう
-
2025/05/20
どんな人でも自己分析は内定への近道